東洋医学の古典に基づいた治療理論を解説します。主に太陽堂漢薬局が学会や研究会などで発表した論文が中心です。
 漢方理論
漢方理論 グルテン、カゼインアレルギーの解消
ノルウェーのオスロー大学の研究では、発達障害の子供さんはグルテンとカゼインの摂取にて尿中ペプチドが増える事が報告されています。グルテンとカゼインの食事制限をすると尿中ペプチドが減少し、発達障害の症状が改善したと報告されています。
 漢方理論
漢方理論 証に合わす食養生
東洋医学を建物に例えれば、土台である心の養生、自ら治そうとする心があります。土台の上に3本の養生の柱。運動。休息、睡眠、入浴。食養生が建ちます。その土台である心の養生と3本柱の養生があって東洋医学という建物が形成されます。
 漢方理論
漢方理論 技を磨く
漢方を始めた頃は本による勉強もですが、感覚を磨く事を中心に教えられました。自分の視覚、聴覚、臭覚、味覚、手技の感覚です。咳を聞いて証を出す。声を聴いて陰陽虚実を判断する。その中でも特に視覚による望診は徹底的に教えられたのを記憶しています。
 漢方理論
漢方理論 漢方薬の副作用について
糸練功の習得は大事だが、症状の訴えがあった時の為に、原因を想定するための知識や、起こりうる副作用についての知識を付けておく必要があると考える。本論文では、著者が経験した実際の症例を交え、漢方薬の副作用について考察する。
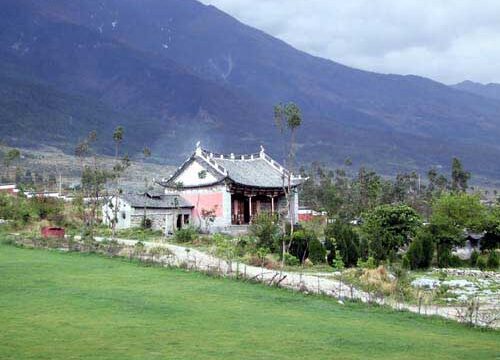 漢方理論
漢方理論 医学の中の糸練功
漢方治療において、糸練功は、大村恵昭先生発案のOTオーリングテストを起源として故入江正先生が開発された入江式FTフィンガーテストより進化発展してきた技術である。発展の経緯を知ることにより今後の展望や方向性、可能性を知ることが出来る。
 漢方理論
漢方理論 X交差治療法
漢方治療において、間中四分画診断は、臍を中心として帯脈と任脉で腹部を四分画にする。身体に異常があると、四分画の上下、左右いづれかで信号を発し、2箇所が陰証、2箇所が陽証の信号を発し対立性である。間中善雄先生に師事された故入江正先生は、間中四分画診断を現在の治療法が完全であるかどうか、最終確認として用いられ我々にも推奨された。
 漢方理論
漢方理論 五色、五行説で考える甘麦大棗湯の働き
東洋医学、漢方で言う心の五味は苦。五色は赤。味で考えるか、色で考えるか、どの物差しで考えるかによって治療法、攻め方が異なって来る。心の正常化を色の物差しで考え、五行説の相生関係、肝と心の関係に当てはめた時、心に属する大棗の独特の働きが見えて来る。
 漢方理論
漢方理論 糸練功上達の鍵
漢方家は誰でも問診を重要視していると思います。問診は患者様の情報から、より正確な証を導き出す為の大事な篩いになります。その篩いに掛けた物の中から選び出す為の糸練功について考えてみます。
 漢方理論
漢方理論 左後頭部を中心とした4箇所の五志の憂への治療と考察
従来の五志の憂の漢方治療では、前頭部の髪の生え際付近を反応穴として使用し治療してきた。今回、前頭部と異なる反応穴3箇所が見つかったので報告する。以下は判明している反応穴である。
 漢方理論
漢方理論 漢方の魅力について
西洋医学では、治りにくい病気や西洋学では諦められている病気が治るというのが漢方の魅力の一つになります。去年の論文でお伝えしました肺MAC症も西洋学では治らない病気の一つと言われています。今回の論文では、東洋医学で治すことが出来る病気についてお伝えできたらと思います。
 漢方理論
漢方理論 薬味に対応する経穴を使った治療の試み
昨年は漢方薬の証に対する鍼灸治療の試みとして、糸練功を使って薬味の作用に対応した経穴を見付け、その経穴を組み合わせる事で漢方薬の証に対しての治療の試みを行いました。今回は薬味の作用に対応した経穴に金粒、銀粒を貼る事で改善効果を高める試みを行いました。
 漢方理論
漢方理論 五臓六腑
漢方医学では五臓六腑という内臓の分類概念を、人体の生理的機能単位の分類方法として用いている。概念は本来は解剖学的な内臓の認識から発展したものなのであろうが、単に解剖学的な内臓の概念の範疇を越えて、人体の生理的機能や精神活動まで、それぞれの臓腑の機能による働きとして捉え、説明がなされている。

