日本漢方の原料である漢方生薬と有名な民間薬をご紹介します。初めての方から専門家まで参考になるよう、気味、帰経、効能、適応とする体質と処方例、民間療法をご紹介。
紅花
紅花はベニバナとも言います。その昔、頬紅として使用されていました。ベニバナの種子から取れる油は、サフラワー油と呼ばれ塗料、石鹸を始め、サラダ油やマーガリンの原料として用いられています。形が大きく、紅色が鮮やかで黄色の部分が少なく、香りが良く、質は柔軟でしっとりしており、茎を含まず、異物の混入がないものを良品とします。
抽出液には、血小板凝集抑制、血管拡張、マクロファージー活性化、動脈血流量増加の薬理作用があります。
気味、薬味薬性
味は辛、性は温
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
心、肝
効能
浮腫みや痛みがある打撲、化膿、痔等の炎症性のうっ血を、血行を盛んにすることによって取り去ります。血行不良を取ることにより腹部の痛みを取り去ります。月経が閉止したり、胎子が死んでしまい出にくくなってしまった時に通じさせることができます。この際、決して無理ではなく、血の巡りやホルモンの分泌を盛んにすることによって体力をつけさせ自然に通じさせます。他の補血薬と併用することによって増血の手助けをします。
適応とする体質と処方例
- 女性の血行不良からおこるうっ血、腰や腹部の炎症や痛みをおこしている方の炎症や痛みの強いものに用います。処方例。折衝飲
- その他の配合処方例。芎帰調血飲第一加減、治頭瘡一方、通導散
- 外用では洗眼剤である蒸眼一方に紅花が配合されています。
民間療法
産前産後の不調。紅花2グラムを1日量とし、3合の水で半量に煮詰め、毎食前30分に服用します。
降香
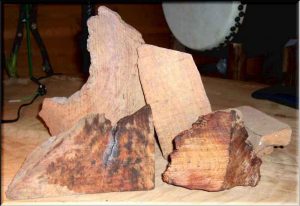
現在、降香の基原植物にはマメ科のダルベルギア、オドリフェラの根の心材をあてる場合と、ミカン科のオオバゲッケイの心材や根をあてる場合とがあります。
オオバゲッケイは中国南部、東南アジアからマレシアにかけて分布するミカン科の常緑樹で、ジャワでは若芽を食用にしたり、根を魚毒の解毒として使用しています。
気味、薬味薬性
味は辛、性は温
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
肝
効能
抗凝血作用があります。冠動脈血流増加作用が認められています。足腰の痛みや心痛、胃痛、打撲傷などに用います。
適応とする体質と処方例
打撲捻挫のある方や胃腸の弱い方、狭心症の方に用います。配合例。竜仙、太陽堂漢薬局開発、伝統漢方研究会保健商品
厚朴

ホオノキの樹及び枝の皮を薬用に使用します。皮はできるだけ厚い方がよく、有効成分が多量に含有されているといわれています。ホオノキの皮は厚いので厚朴と呼ばれています。
和厚朴。現在の日本の漢方で使われる厚朴です。皮部が厚く、充実し、わずかに芳香性で味は苦いものを用いますが、偽者で代用品です。唐厚朴。油じみて紫黒色を呈し、表面に光輝ある結晶を折出し、味は芳香性で辛いものを最上品とします。
正倉院に勅封されております唐厚朴は、半管状で厚く殆ど屈折せず、今なおマグロノルの白色の光輝ある粒状晶が星のように全面にキラキラ点在しており、最上等品であるが精油成分が殆ど揮散し味は全くないようです。マグロノルは、厚朴の抽出液で、抗ストレス潰瘍、胃液分泌抑制、胃粘膜出血阻止などの働きがあります。
気味、薬味薬性
味は苦、辛、性は温
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
脾、胃、肺、大腸
効能
漢方では陽実証の緩解剤であり、食毒や水毒による胸腹部の膨満、腹痛に用います。すなわち胃腸機能を促進する作用がある傍ら、去痰、利水および一種の鎮静作用があります。
薬徴によれば「厚朴は胸腹の胸から腹にかけて膨満する張満を主治するなり、傍ら腹痛を治す」としています。胃腸が悪く吐いたり、下痢したりする激しい状態を鎮めながら胃に働きます。胸、腹の張りを治します。ただし対処的なので原因を取り除く場合は他の薬を併用する必要があります。気分的な逆上せを含めた上気の状態を引き下げます。
適応とする体質と処方例
- 胃が弱っているために、余計な水分を排泄できず体内に停滞し、それが原因となって、喉に焼肉の一片または梅干の種のようなもの引っかかっている様な感じのある方。取り越し苦労が多く塞いだり心配性になったりもする方。処方例。半夏厚朴湯
- その他の処方例。藿香正気湯、平胃散、柴朴湯、神秘湯、小承気湯
民間療法
- 飛騨高山といえば朴葉料理の本場であり、漬物や佃煮などなんでも朴葉の上に乗せて暖めて食べる風習があります。
- 朴葉の中には芳香成分が含まれていて加温につれて発散する芳香は食べ物の風味を一層良くし、朴葉味噌はその代表的なものだと思われます。
粳米

インド北部から中国の雲南を原産として、アジア及び世界各地で食用として広く栽培されているイネ科のイネの穀粒、すなわち、うるち米を玄米にして用います。
コメは粘性によって粳米と餅米に分けられ餅米は粳米よりも粘性が強くなります。
気味、薬味薬性
味は甘、性は平
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
脾、胃
効能
胃腸を整え元気をつけ口渇や下痢に用います。
適応とする体質と処方例
逆上せがきつく、咳き込んで顏が赤くなり喉に不快感を感じ、咽喉部に炎症を起こし苦痛を生じ、乾いた咳をしている方に用います。処方例。麦門冬湯
牛黄

牛黄は、牛または水牛の胆嚢や胆管に出来た結石です。中国最古の薬物書、神農本草経では、牛黄は上薬として収載されています。上薬とは、毒が無く多量に長期間飲み続けても副作用がなく、命を養う不老長寿の薬を意味します。
希少価値が高く、古くから高貴薬として用いられてきました。様々な作用がありますが、中でも強心作用に優れています。
気味、薬味薬性
味は苦、性は涼、小毒あり
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
心、肝
効能
鎮静作用があります。高熱、意識障害、熱性痙攣、煩躁、脳卒中などに用います。強心作用として、狭心症の発作を鎮める働きがあります。その他、肝機能を改善する働きがあります。
適応とする体質と処方例
炎症により高熱があり意識障害、うわ言、痙攣などの症状がでている方に用います。処方例。牛黄清心元、安宮牛黄丸


