日本漢方の原料である漢方生薬と有名な民間薬をご紹介します。初めての方から専門家まで参考になるよう、気味、帰経、効能、適応とする体質と処方例、民間療法をご紹介。
金銀花
スイカズラの花を採って陰干ししたものです。スイカズラの葉は忍冬になります。スイカズラの花は白い花ですが、白い花を開いてからは赤、黄、白とかわっていくので金銀花の名を得ました。蜜槽から甘い蜜を出すので子供たちは喜んで蜜を吸うようです。このスイカズラの葉は寒くなっても枯れず、冬でも耐え忍ぶところから忍冬ともよばれています。漢方の抗生物質とも呼ばれています。
気味、薬味薬性
味は甘、性は寒
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
心、肺、脾、胃
効能
腸管を蠕動させ緩下の働き、または利尿、収斂作用によって化膿を取りさります。化膿を取りさるのに必ず殺菌力がないといけないことはありません。代謝を盛んにしておけば、利尿、緩下によって化膿を取りさることができます。
適応とする体質と処方例
- 化膿でじくじくとしてなかなか治りにくい方。処方例。托裏消毒飮
- 梅毒、便毒、結毒など梅毒の諸症状のある方。処方例。香川解毒散
金箔
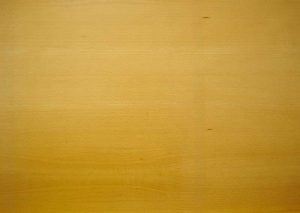
金の薄片です。
気味、薬味薬性
味は辛、性は平
効能
自律神経の亢進を鎮めます。解毒の効果があります。化膿症に用います。
適応とする体質と処方例
高血圧にともなう動悸、手足のしびれ、肩のこり、のぼせ、耳鳴り、めまい、頭重感のある方に用います。処方例。牛黄清心元
銀杏葉

銀杏樹の葉を乾燥したものです。
気味、薬味薬性
味は苦、性は寒
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
心
効能
血清コレステロール値を低下させます。冠状動脈の拡張作用があります。
適応とする体質と処方例
太陽堂漢薬局では補助薬として用いています。
民間療法
種子の銀杏は咳止めに用います。
苦参

苦参はクララの根です。苦参の煎液は非常に苦く目に入るとクラクラとするのでクララと言われるようになりました。苦参は苦い、参は人参を表わしています。
人参は特効薬の代名詞で、苦い薬草ですが、効力があって人参のように特効のある薬草であるという意味です。
気味、薬味薬性
味は苦、性は寒
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
心、肝、小腸、大腸、胃
効能
胃酸過多、胃炎に用います。逆に胃アトニーには効果がありません。それのみならず虚弱者には副作用があります。解熱作用があります。風邪などの時の熱でなく、肝臓の炎症や慢性腹膜炎、卵巣の炎症や充血に用います。膀胱、腎臓の炎症で熱があって、小便の排出が不十分である時に炎症を取り自然排出を促します。
適応とする体質と処方例
血液の循環が悪く、腎、膀胱に熱があって口が渇き、うっ血に熱が合わさった血熱を生じ、尿の排出がうまくいかずに、皮膚のできものや炎症を起こされている方に用います。処方例。消風散、三物黄芩湯
民間療法
- 疥癬に20グラム外用で。煎汁で患部を洗うか、生の根の汁を塗る。
- うじ虫駆除に、乾燥した葉を細かくもんで、便壷に入れる。
枸杞子、地骨皮

枸杞には3つの使用方法があり、赤い実が枸杞子、倒卵型の葉を枸杞葉、根を地骨皮といいます。枸杞の変形物に、茎に刺を有しているものがありイヌグコ、オニグコというもので薬用には刺のない物の方が良いです。
気味、薬味薬性
味は甘、性は平
帰経。東洋医学の臓腑経絡との関係
肝、腎
効能
肝臓に脂肪が貯留するのを防いだり、脂肪肝を治したりします。ホルモンの分泌腺を治療する力があります。老人になると起こりやすい、血管がもろくなったり尿の出が悪くなったりするのを良くします。肺結核の熱に良いです。
適応とする体質と処方例
普段から胃腸が弱く、冷え症で神経質で取り越し苦労が多く、尿が濃い方などに用います。処方例。清心連心飲
民間療法
- 疲労回復に内服で。枸杞子200グラムに、グラニュー糖200グラムを加えて、ホワイトリカー1.8リットルに約2ヶ月漬け、毎日ワイングラス1杯程度飲む。
- 高血圧5から10グラム内服で。乾燥した枸杞葉を煎じて服用。
- 山菜料理、若葉をさっと茹で、おひたしや和え物に。クコめしは若葉をさっと塩茹でして刻み、味付けして炊いた御飯に混ぜる。


